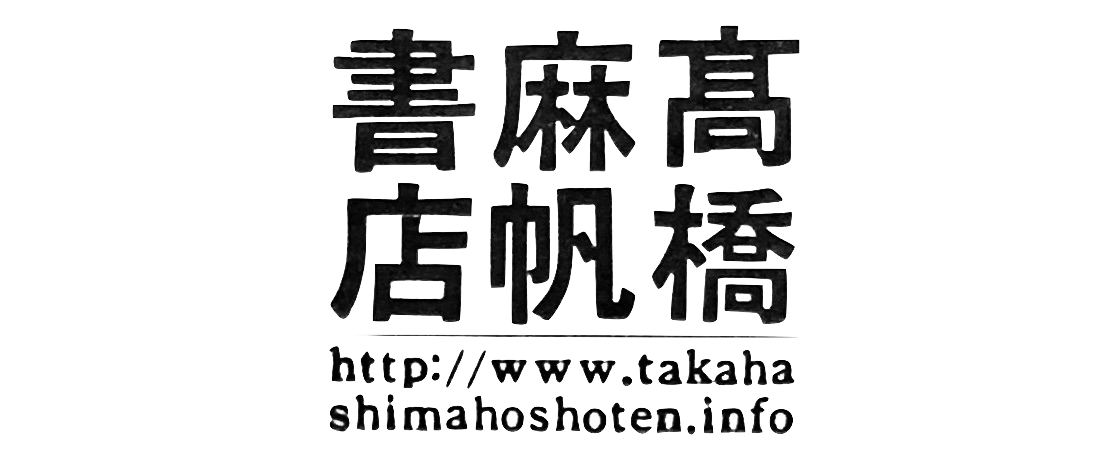2021/09/06 21:31
週に一度、アルバイトに来てくださるHさんと修復の勉強を始めました。
ですので、この本は写真より良い状態になっています。
本屋さんそれぞれ修復には試行錯誤、お店によってやり方が違うようです。
ちょっとした直しだと、プロの修復家さんにお願いするより、
さっとやってしまった方が楽な場合もあるのです。
〜〜〜
大切な本をお持ちで、修復したいと、プロの方にお願いしたい方、
ご相談ください。おつなぎいたします。
(私も最近入荷本を二十冊ほどお願いしていたのが、つい最近仕上がって来ました。
自分でも実践してみてから改めて眺めるプロの技は新鮮でした。)
〜〜〜
19世紀半ば以前は、西洋では、版元で表紙のデザインを一律に決めて本を綴じる伝統はありませんでした。
本の表紙は持ち主が決め、製本工房で一点ものとして誂えるものでした。
素材は革にするか、羊皮紙にするか、厚紙か薄い紙か。背だけ別素材にすることも出来ます。
またタイトルをどのようなフォントで背に刻印するのかや、表紙にどのようなデザインの飾りを施すのかなどなど、
無限の選択肢がありました。
古い本を数々手に取っていると、本を綴じたかつての持ち主の気持ちを自ずから想像するようになります。
そして、本の図版が逆に綴じられているのが返って喜ばれたり、
異なる本二冊分が一冊の本に綴じられているのが面白がられたり、
足りないページを長年かけて求めて、製本家の方の力を借りて綴じ直して完璧な一冊にしたりする、
本好きの自由な世界に入って出られなくなってしまいます。
例えば、このシュテファン・ゲオルゲの革装の本は版元の装幀ではありません。